受賞作品









Japan Leather Award
2025

グランプリ
大阪府
ウエダ トモユキ
TOMOWORKS
審査員長 総評
本来こうした性能に重きをおく機器は、数年使って評価すべきものである。しかしながら作者の取り組みに審査員一同が共感した。
特筆すべきことは
① 量産ではできない、レザークラフト技術の中にヘッドフォンの進化の可能性を見つけたこと。
② 革の材料特性を十分に理解し、音質を高める利点があることを再定義していること。
③ 近年の消費者とモノとの関わり方を、加水分解なし、長く愛せるというサスティナブル視点から提案していること。
自然素材では木材(スピーカー)が音質を高める特性があるとされ、多くのオーディオに採用されているが、革もその市場に加わる可能性が十分ある。まだプロトタイプ感は否めないが、音質、デザイン、着け心地等、五感を満足させるに十二分のヘッドホンの提案であり、革製品のジャンルを広げる秀逸な作品と言えよう。
各部門・各賞受賞作品
ベストプロダクト賞
フットウェア部門
三上 良弘
株式会社ネーカーズ
京都府
審査員長 総評
異素材のコラボは野暮ったくなるのが常である。日本の伝統織物と革製品のコラボは、これまでも多く審査してきたが、この作品のように違和感なく自然に受け入れられるものは記憶にない。採用されている西陣織の独特なパターンデザインが靴全体にリズムを与え奏功している。
革の“剛”と織物の“柔”の対比は、日本オリジナルとも言える美しい造形に結びつき、欧米の製品との違いを鮮明にする。
こうしたデザインは易々とできるものではなく、作者の長い期間かけての異業種交流、共同作業が結びついた結果と思う。伝統工芸を観光立国の目玉の一つにする政府の取り組みにも大いに便乗し、新しい暮らしの靴をますます提案して欲しいと思う。
バッグ部門
野沢 浩道
個人
栃木県
審査員長 総評
作者の技量やデザイン力は周知のことだが、改めてその溢れる知性に感銘を受けた。
皮革という生き物を原料にする上で、作品の決め手として最も大切なのは知性ではないだろうか、と考えさせられた。
繊細な造形感覚から作られた腐食した金属フレームが「詫びを描写、不変さ」を表し、「栃木レザーの変化する」材料特性と対比させる知には美の秩序がある。
また「野性味溢れる《猪×蛇》を選択。《亥》と《巳》は”向かい干支”〜反対の性質を持ち、足りない部分を補い合う相性の良さがある」という物語には、風習文化がある。
欧米化した人とモノとの関係を一度ほどき、もう一度伝統文化を見直し新しく結び直す、そんなアーティスティックな知性がこの作品の源流である。今後飛躍を目指す若い作家の方々はこの二つの作品からぜひ多くのことを学び、ジャパンオリジナルに挑戦して欲しいと思う。
※本作品は、2つの作品でベストプロダクト賞となりました。
(左の作品)
(右の作品)
ウェア&グッズ部門
小川 陽生
GNUOYP(ニュピ)
東京都
審査員長 総評
今財布が面白い。
ここ数年さまざまな財布の提案を見てきたが、財布ほど変化が激しいジャンルは皮革業界において他にない。スマホが財布がわりになったのだから当然と言えば当然だ。
財布の重厚さは不要となり、軽くカラフルで、小さくかつ薄いものに変わってきた。いわゆるオシャレ財布たちの出現である。
そうした中にあり、このTENMIZO GAMAGUCHI #3は、「今時のクリエイターとは異なる、昔良き時代のメーカーさん」を結集し、“今の財布”を提案している。王道を歩む姿勢がいい。財布の機能美と“がま口”のワイルドさが一体となったデザインが新鮮で魅力的である。
作者が挑んだ「絶滅危惧手の天溝職人」とのタッグなどは、社会運動的な側面もあり、意義ある成果として今後の皮革業界を刺激することだろう。
フリー部門
山口 洋平
atelier Ripple
香川県
審査員長 総評
ハンディファンを持つ人が増えた。この酷暑ではやむを得ない現象だが、いつ見ても違和感がある。
ハンディファンを持つ現代人を見て、ある社会学者も「自分だけ良ければ」の世を危惧していた。
そこまで大袈裟には考えないとしても、ハンディファンは暑さを凌ぐため(−の道具)だが、うちわは涼を楽しむ(+の道具)ためにある。江戸の浮世絵にも「うちわ」を持つ浴衣美人が多く描かれている。
「うちわ」=和紙と決めつけていたため、革素材が「うちわ」にこれほど適しているとは想像もつかなかった。特にやや縦長で小ぶりな造形が現代的で、“粋”なデザインに仕上がっている。
「このポケットにカードを入れれば、何も持たずこれだけでお出かけできますね」(審査員)、
これからの温暖の世、革の「うちわ」は長い夏の生活必需品になりそうである。
フューチャーデザイン賞
フットウェア部門
木下 実
課題商店
東京都
審査員長 総評
インフルエンサーなどを巧みに活用するデザイン手法。
そんな情報操作を武器に、靴に新しい息吹を吹き込む“とらわれない発想”は、製品デザインというより情報デザインの範疇であり、その新しい手法、姿勢を評価したい。また、そうした新しい手法がブレない制作に結びつき、質の高い造形として靴に物語性や生命感を与えて、見る者、使う者に今までにない暮らしや情景を想像させる。
自分だけ満足する内向きなデザイン提案でなく、情報デザイン的な手法を取り入れ、周りの人と共に楽しむ外向きのデザイン提案は、これからの皮革産業のデザインソリューションとしてとても効果的なやり方と言えるだろう。
バッグ部門
椎名 賢
Ken Shiina Design Laboratory
兵庫県
審査員長 総評
モチハコブカタチの理想は、一つのカバンでありながらモノに応じて大きくなったり小さくなったりすること。重いモノも人力で運べ、究極は、いざという時、水も漏らさず運べることだろう。そんなカバンは今日の先端技術を持ってしても実現が難しい。
この作品「slit to stretch」を手に取った時、理想を真摯に追求する作者の姿が浮かんできた。彫刻家が素材に向き合い、新たな理想を追い求めるように、モノが溢れた世にありながら常に理想のモチハコブカタチを希求する仕事ぶりは見本のようである。皮革の材料特性と内部に使用されている素材特性が、かつてない伸縮性を実現、薄い書類を入れてもフットサルのボールを入れても、どちらの姿も美しく様になる。
ウェア&グッズ部門
加藤 友樹
有限会社T.M.Y’s
東京都
審査員長 総評
革ジャンの重さがない。物理的な重量だけでなく、視覚的にも触覚的にも重さがないのである。また「普通」を真剣に手を抜かずに取り組んでいるためか、モードが陥りがちな独りよがりな感じもない。
柔らかな羊革の触り心地や軽快でスポーティな佇まいがそれに寄与しているのか。
クラフトマンシップがあって成立する革製品は、どうしても作者のこだわりが前面に出て、作り手目線になりがちだがこの製品にはそれがない。消費者オリエンテットに徹した姿勢は好感が持てる。
最高級の水染め、自社での染料仕上げ、牛革ではなくあえて羊革にこだわったクラフトマンシップに蓋をした、“総合知”とも言えるバランスの良い大人のデザインデレクションが秀逸な作品につながった。
フリー部門
ウエダ トモユキ
TOMOWORKS
大阪府
審査員長 総評
本来こうした性能に重きをおく機器は、数年使って評価すべきものである。しかしながら作者の取り組みに審査員一同が共感した。
特筆すべきことは
① 量産ではできない、レザークラフト技術の中にヘッドフォンの進化の可能性を見つけたこと。
② 革の材料特性を十分に理解し、音質を高める利点があることを再定義していること。
③ 近年の消費者とモノとの関わり方を、加水分解なし、長く愛せるというサスティナブル視点から提案していること。
自然素材では木材(スピーカー)が音質を高める特性があるとされ、多くのオーディオに採用されているが、革もその市場に加わる可能性が十分ある。まだプロトタイプ感は否めないが、音質、デザイン、着け心地等、五感を満足させるに十二分のヘッドホンの提案であり、革製品のジャンルを広げる秀逸な作品と言えよう。
学生部門最優秀賞
国田 來愛
兵庫県立姫路工業高等学校
兵庫県
審査員長 総評
まず「どうして大阪のおばちゃんは…」という疑問を持ったこと、これが出発点なのがいい。
そして、大阪のおばちゃんの趣味を批判するのではなく、自らその気持ちに寄り添い、ウチに入っていく優しい気持ちがいい。
批判は何も生み出さない、そう美術学校の恩師に習った。この作品はそれを証明している。
この作品は作者の観察眼、デザインリサーチの成果が生み出したこと。また、それをさらに従来の手法ではなく、コストも視野に入れた柔軟思想で若々しいデザインとして作り上げている点も大いに評価した。
大阪のおばちゃんもびっくりするだろう“インパクトあるデザイン”、きっと若者も好きになるだろう。
アーティスティックデザイン賞
井藤 憲一郎
創作工房 井藤
福井県
審査員長 総評
ガンダムの手のようなバッグは、まさに「HAND BAG」である。そんな作者のユーモアの中に 作品への想い、時代へのメッセージを感じとった。
スマホが普及しバッグに何を入れるのかさえ定かではなくなっている昨今、
バッグは「何かをモチハコブ」という機能性を超えて、その人を表す持具(アトリビュート)としての情報端末に昇華している。
欧米のファッション業界も、混迷するモードを引っ張る役割として衣服以上に小物、バッグ類に新しい流行の扉を開く可能性を見ているようだ。
機能性を超えたこの「HAND BAG」は様々なメッセージを我々に投げかけている。
受賞者インタビュー
ベストプロダクト
~Tomokita~
瀧本 武

入賞
No.0035
個人
永桶 拓郎

入賞
No.0037
個人
橋本 啓佑

入賞
No.0068
個人
佐貝 洋司

入賞
No.0141
(株)リーガルコーポレーション
佐藤 健

入賞
No.0169
個人
FUMOTO 一乃麓

入賞
No.0204
株式会社ネーカーズ
三上 良弘

受賞
No.0262
株式会社 いたがき
寺田 尚由

入賞
No.0293
有限会社オベリスク
石橋 善彦

入賞
No.0010
個人
野沢 浩道

受賞
No.0013
株式会社 鞄工房山本
正木 季子

入賞
No.0039
Suenaga Design Studio
末永 るみえ

入賞
No.0041
エース株式会社
佐藤 周平

入賞
No.0048
アトリエハトリベ
福 裕一

入賞
No.0161
個人
高橋 幹大

入賞
No.0232
株式会社村瀬鞄行
井戸田 和之

入賞
No.0272
GNUOYP(ニュピ)
小川 陽生

入賞
No.0285
アールアトリエ中目黒
小花 亮介

入賞
No.0327
billknocks
古田 光

入賞
No.0334
ルボア株式会社
森 直之

入賞
No.0006
バンビマニュファクチャリング株式会社
矢野 悟
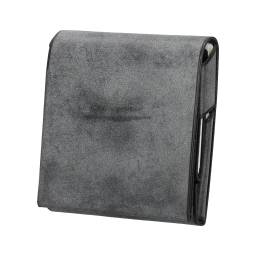
入賞
No.0025
GNUOYP(ニュピ)
小川 陽生

受賞
No.0259
有限会社T.M.Y’s
加藤 友樹

入賞
No.0386
atelier Ripple
山口 洋平

受賞
No.0022
セイコーウオッチ株式会社、株式会社リーガルコーポレーション
合田 貴子

入賞
No.0361
フューチャーデザイン
イシヅカ靴店
石塚 昌美

入賞
No.0023
shoes studio tomo.ni
中口 智仁

入賞
No.0062
課題商店
木下 実

入賞
No.0063
課題商店
木下 実

受賞
No.0064
個人
瀬藤 貴史

入賞
No.0076
関口善大靴工房
関口 善大

入賞
No.0146
(株)リーガルコーポレーション
伊藤 敦史

入賞
No.0168
有限会社T.M.Y’s
加藤 友樹

入賞
No.0170
「ATSUSHI INOUE」
井上 篤

入賞
No.0264
個人
野沢 浩道

受賞
No.0014
アトリエハトリベ
福 裕一

入賞
No.0163
株式会社村瀬鞄行
岡田 憲樹

入賞
No.0217
創作工房 井藤
井藤 憲一郎

受賞
No.0273
Ken Shiina Design Laboratory
椎名 賢

受賞
No.0348
chelsea leather art work
北崎 厚志

入賞
No.0356
有限会社オベリスク
石橋 善彦

入賞
No.0012
有限会社T.M.Y’s
加藤 友樹

受賞
No.0171
革所
谷口 諒司

入賞
No.0295
TOMOWORKS
ウエダ トモユキ

受賞
No.0021
個人
谷川 史憲

入賞
No.0033
(有)グランツ
高松 智明

入賞
No.0097
個人
谷藤 嵩

入賞
No.0206















